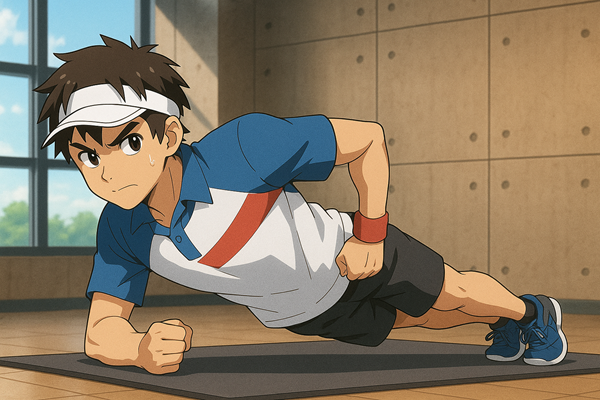動体視力のトレーニングについてです。
【武井壮】動体視力や反応速度を鍛えるトレーニング。日常生活でやっていた事【切り抜き】
動体視力は「慣れ」が大切です
動体視力は特別なトレーニングで鍛えるというよりも、日常の中で「慣れ」を積み重ねることが重要です。動いている対象に自分の体を合わせる習慣をつけることで、自然と適応できるようになります。
日常生活での工夫が効果的です
街を歩きながら葉っぱの先端を指先や肘で触る、キャッチボールでグローブのいろいろな部分で捕球するなど、普段から異なるシチュエーションで体を動かすことが有効です。こうした習慣が、スポーツに応用できる基礎となります。
予測力と反応の組み合わせが鍵です
スポーツでは、経験に基づく「予測」も重要です。状況に応じて起こり得る展開をあらかじめ絞り込むことで、実際のプレー中に素早く反応できるようになります。反応してから動くのではなく、反応しながら動けるようになることが理想です。
まとめ
動体視力や反応スピードは、特別な練習よりも日常的な習慣づけと経験による予測力の積み重ねで養われます。体を動かしながら多様な状況に適応する練習を日常に取り入れることが、スポーツにおいても大きな力となります。
動体視力トレーニング 動体視力の仕組みと鍛え方 2018年と2019年の論文より【新庄剛志選手のプロ野球選手復帰の鍵】
動体視力とは何か
動体視力とは、動く物体を正確に捉える力のことです。バスケットボールや野球、サッカー、卓球など多くのスポーツでパフォーマンスを高める重要な能力とされています。
スポーツにおける動体視力の重要性
- 野球:バッティングや守備においてボールの軌道を予測できるほか、バランス能力の向上によりピッチングのコントロールも改善される可能性があります。
- サッカー:久保建英選手のように首を頻繁に動かして周囲を把握するプレーには高い動体視力が必要です。これにより試合中の状況判断がスムーズになります。
静的視力との違い
静的視力は眼の構造的な問題に左右され、メガネやコンタクトで矯正可能です。一方、動体視力は眼球運動と深く関係し、手ぶれ補正付きカメラのように「動きの中で対象を追う能力」に例えられます。
動体視力は鍛えられるのか
研究によると、動体視力も筋力と同様に「過負荷の原則」が当てはまるとされ、適切なトレーニングで向上可能です。特に5歳~15歳で急速に発達し、20歳以降は加齢とともに低下するため、意識的なトレーニングが重要です。
動体視力を鍛える4つの方法(テヘラン大学 2019年研究より)
- 交互注視:左右のペンなどを交互に素早く視線で追う。
- 物体追従:首を固定し、動かした物体を目で素早く追う。
- 首回転注視:物体を固定し、首を大きく回しながら対象を視認する。
- 複合運動:物体を動かしつつ、首を逆方向に回して視線を追従させる。
これらを週6日、1日10分程度、4週間継続することで、動体視力とバランスの向上が確認されています。
補足:検査方法の課題
動体視力の測定方法はまだ確立されておらず、今後の研究によって新しい知見が得られる可能性があります。
まとめ
動体視力はスポーツに直結する能力であり、年齢や経験によって変化します。日常的にトレーニングを取り入れることで、競技力の向上やパフォーマンス改善につながります。
【動体視力の基礎知識】スポーツビジョンをトレーニングして大谷翔平選手を目指そう
大谷翔平選手と動体視力トレーニング
大谷翔平選手がリハビリ期間中に動体視力トレーニングを取り入れていることで注目が集まっています。動体視力は野球選手にとって重要ですが、これだけでパフォーマンスが大きく向上するわけではなく、反応能力や筋力など総合的な運動能力が必要です。
静止視力と動体視力
- 静止視力:止まっている物体を識別する力(学校の視力検査で測定)。
- 動体視力:動いている物体を見分ける力。
野球では両方の視力が必要で、特にバッティングや守備では動体視力と反応速度の連動が欠かせません。
スポーツビジョンとは
アメリカでは「スポーツビジョン」と呼ばれる総合的なビジョンケアが普及しています。
主な取り組みは以下の通りです。
- 目の怪我の予防・管理(スポーツ眼外傷の研究・対策)
- 視機能の検査・改善(普通の視力検査では分からない機能を評価)
- 専門的なコンタクトレンズや矯正手術の提供
- 視覚機能の測定(動きの速さ、奥行き把握、両眼の協調など)
- 視機能強化トレーニング(科学的エビデンスはまだ不足)
- パフォーマンス向上のための視覚戦略コンサルティング
スポーツビジョンの歴史と研究
- 1978年:アメリカ眼科学会にスポーツビジョン部門が設立。
- 1980年代:資格能力とパフォーマンスの研究が始まる。
- 2010年代以降:ビジョントレーニングと野球のバッティング向上に関する研究が増加。
- 近年:デジタルビジョントレーニングやデータ分析が進み、MLB球団でも導入が広がっている。
日本における取り組み
日本では大学病院のスポーツ眼科や体育系大学で研究が進められています。今後は世界のスポーツビジョン組織と連携し、トップアスリートの育成や現場へのフィードバックが期待されています。
実践的なアプローチ
- 静止視力だけでなく医学的なスクリーニング検査を受けることが推奨されます。
- 適切な矯正後には「視覚反応トレーニング」や「コンディショニングチェック」で体の状態を把握し、トレーニング効果を高めることが重要です。
まとめ
動体視力は野球をはじめとするスポーツに欠かせない要素ですが、それだけでは不十分です。総合的な運動能力、栄養、心理面のサポートと合わせて鍛えることで、初めてパフォーマンス向上につながります。今後は日本でもスポーツビジョンの研究と実践が広がり、より科学的なアプローチで選手を支える環境が整っていくことが期待されます。
大阪初!動体視力も科学で鍛える…子ども専用 最先端のスポーツジムとは
科学的アプローチによるトレーニング
- 低酸素トレーニング:特殊なマスクで標高2,500mの環境を再現し、心肺機能や持久力を効率的に鍛えることが可能です。
- スポーツビジョン強化:動体視力や視野の広さを鍛えるトレーニングを導入し、試合中の判断力や反応速度を高めています。
実際のトレーニング例
- 視野拡大トレーニング:画面に一瞬出る数字や丸の位置を認識する練習で、周辺視野を強化。
- データの「見える化」:トレーニング結果を数値化し、自分の強み・弱みを把握。子どもたちのモチベーション向上につながっています。
【ビジョントレーニング】バドミントン【視力】レシーブをうまくする
ビジョントレーニング例:親指を交互に見る。