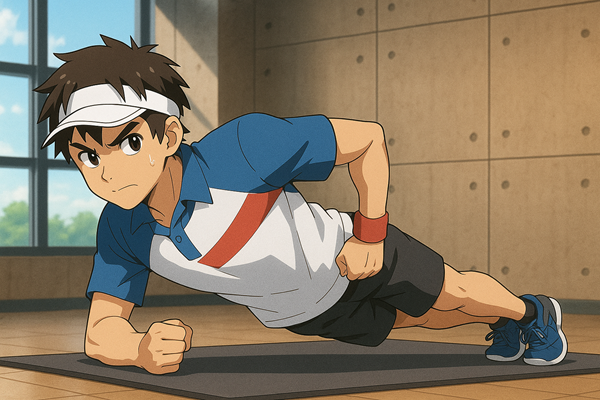ソフトテニス 体幹トレーニングで上達 おすすめ5選です。
筋トレと体幹トレーニングは、どちらも筋肉を鍛えるトレーニングですが、主な目的と鍛える部位が異なります。
筋トレは、全身の筋肉を鍛えて筋力や筋肥大を向上させるのが目的で、主にアウターマッスルを鍛えます。
一方、体幹トレーニングは、体の中心部の筋肉(インナーマッスル)を鍛えて、姿勢やバランスを改善するのが目的です
ソフトテニスのプロ選手は硬式テニスのプレーも参考にしています。硬式テニスのエッセンスも吸収することで、ソフトテニスの上達にも活きると思います。
【ソフトテニス】体幹を鍛えてストロークスピードアップ!ソフトテニス選手向け最新体幹トレーニング5選!
トレーナーのマックスさんとコーチのうっちーさんが、ソフトテニス選手のための体幹トレーニングを5種目紹介しています。今回のポイントは「静止する筋トレ」ではなく、「動きの中で体幹を安定させる」ことに重点を置いた内容です。
なぜ一般的なプランクでは足りないのか?
プランクのように体を固めるトレーニングは、ラグビーやサッカーのようなコンタクトスポーツに有効ですが、ソフトテニスではあまり活用されません。ソフトテニスに必要なのは、動きの中で瞬時に体幹を使う能力です。
トレーニングメニュー5選
1. ベアクロール
四つん這いで膝を少し浮かせた状態をキープしながら前後に移動します。背骨をまっすぐに保つことで、体幹にしっかり効かせることができます。
2. インバーテッドクロール
手を後ろについてお尻を持ち上げ、前後に移動します。肩甲骨、背中、二の腕、腿裏など、普段使わない筋肉を刺激できる全身運動です。
3. ショルダータッチ(プランク姿勢)
腕立て伏せの姿勢で片手ずつ肩にタッチします。体がぶれないようにキープしながら行うことで、体幹の安定性が向上します。難しい場合は四つん這いでもOKです。
4. スプリットスタンス抵抗トレーニング
足を前後に開いた姿勢で手に外からランダムな負荷をかけ、体幹でそれを支えます。回旋運動への耐性を高めることで、腰や体の回転速度が向上します。
5. 回転サイドプランク
仰向けから回転してサイドプランクの姿勢を瞬時にとるトレーニングです。スポーツに必要な「瞬間的な力の発揮と安定」を鍛えることができます。
トレーニングの目安とまとめ
各種目は10回を3セットを目安に実施するのがおすすめです。これらを取り入れることで、テニスに必要な機能的な体幹が鍛えられ、プレーの質も向上します。
【ソフトテニス】体幹トレーニング解説!
体幹トレーニングの重要性
今回の動画では、体幹トレーニングの基本について解説しています。日常生活やスポーツにおいて、体幹は姿勢の安定や動きの土台となるため、非常に重要です。柔軟性では補えない部分を、体幹でしっかりと支える力を養うことが目的です。
実施するトレーニングメニュー
1. 基本のフロントプランク
両肘をついて体を一直線に保つ姿勢です。腰が上がったり下がったりしないように注意し、背中からかかとまで真っ直ぐを意識します。最初は30秒、慣れてきたら1分を目安に行います。
2. サイドプランク(左右)
体を横向きにして肘と足で支える姿勢です。お尻が上がったり、体が曲がったりしないように、一直線を意識して行います。左右ともに行い、それぞれ30秒~1分程度を推奨しています。
3. ヒップリフト(ブリッジ)
仰向けに寝て、お尻を持ち上げるトレーニングです。足を少し前に出すと負荷が上がります。慣れてきたら片足を上げて強度を上げる方法もあります。30秒〜1分を目安に行います。
トレーニング時の注意点
体幹トレーニングは「形を崩さず正しいフォームで行うこと」が最も大切です。楽な姿勢でやってしまうと効果が減少してしまうため、意識して取り組みましょう。特に腰や肩の位置がブレないように注意が必要です。
まとめ
体幹を鍛えることで、競技中の安定性が高まり、厳しいボールにも対応できる力が養われます。継続して行うことで成果が出やすくなりますので、無理のない範囲で毎日の習慣にしていきましょう。
プロから学ぶ!体幹トレーニングの一部を公開!!
【ソフトテニス】試合で緊張する人におすすめ!プランクより優秀なソフトコアの鍛え方!
試合で緊張してしまう人のためのソフトコアトレーニング
今回のテーマは「試合で緊張してしまう人」に向けた体幹トレーニング「ソフトコアトレーニング」の紹介です。緊張を悪いものと捉えがちですが、実は適度な緊張とリラックスのバランスが最もパフォーマンスを発揮できる状態です。
ソフトコアとは?
従来の「プランク」のような体をガチッと固める体幹トレーニング(ハードコア)ではなく、柔らかく安定させる体幹を養うのが「ソフトコアトレーニング」です。緊張しすぎると肩や首に力が入り、体幹が抜けてしまいます。そこで、適度な緊張を保ちながらリラックスして動ける体をつくるのが狙いです。
ビーム(木の棒)を使ったバランストレーニング
ホームセンターなどで手に入る木の棒をビームとして使い、その上を歩くトレーニングです。
- 肩や首に力を入れすぎるとバランスが崩れやすく、リラックスしすぎると落ちてしまいます。
- 適度な緊張状態を体で覚えるのに最適な練習です。
- 前進・後退・ターンなど様々な動きでバランス感覚を養います。
ラケットやダンベルを使った応用トレーニング
- 頭の上にラケットを持って歩くことで、重心が高くなり不安定さが増します。
- ダンベル(片手・両手)を持って歩くことで、足裏の荷重感覚や体幹の反応が高まります。
- ケトルベルを使った「ゼロポジション」では、肩甲骨まわりや腹斜筋にも効果があり、ケガ予防にもつながります。
足裏の感覚と踏ん張る力を養う
現代人は靴に慣れすぎて、足裏で体重を正しく支える感覚が鈍くなっています。このトレーニングでは、足裏からの情報を正確にキャッチし、踏ん張る力を養うことが目的です。これはジャンプやサイドステップにも直結します。
トレーニングのまとめ
ソフトコアトレーニングは、体を「ガチッ」と固めるのではなく、しなやかに安定させる力を養う内容です。これは試合での緊張に負けず、リラックスしすぎず、最高のパフォーマンスを引き出すための土台づくりになります。
【テニス/体幹トレーニング解説編①】テニスの為の体幹トレーニング解説編!腹圧+股関節・肩を使うトレーニングメニュー 腹圧のやり方も解説【菅尾アスレティックトレーニングセンター】【はちおうじ庭球塾】
本動画では、アスレティックトレーナー兼テニスコーチの菅尾さんが、腹筋群(体幹部)を機能的に鍛えるトレーニングメニューを紹介しています。目的は単なる筋トレではなく、テニス中に「お腹に力を入れて安定したスイング」を実現することです。
なぜお腹に力を入れるのが難しいのか?
多くの人が「お腹に力を入れて」と言われても、実際には肩や腕に余計な力が入りやすく、スイングがスムーズにできなくなりがちです。そこで、お腹に力を入れつつ、上半身や下半身をスムーズに動かす「腹圧(ふくあつ)を活用する動き」を身につけることが重要です。
トレーニングメニューの概要(計7種)
① セッティング(基本姿勢)
- 仰向けで膝を曲げ、腰と床の隙間に手を入れて腹圧をかける。
- 息を吐きながらお腹をへこませて手を潰すイメージ。
② 足の引き上げ(片足ずつ)
- お腹を意識しながら足を引き寄せ、腹圧と連動して股関節を使う。
③ 膝を伸ばした足上げ(片足ずつ)
- 膝を伸ばしたまま片足を持ち上げる。腹筋への負荷が高まる。
④ 両足上げ
- 両足を同時に持ち上げる。後半は足を床につけずさらに強化。
⑤ 横への開脚(股関節の外旋)
- 足を外側に開く動きで、お尻の外側(中殿筋など)を刺激。
- つま先は常に上向きに保つこと。
⑥ 上半身の腹圧強化(万歳)
- 肩甲骨を床から少し浮かせた状態で、万歳運動を行い腹筋を意識。
⑦ 上半身の腹圧強化(扇型運動)
- 腕を左右に動かし、腹圧を保ったまま肩周りを連動させる。
初心者向けアドバイス
- 「お腹がキツイ」と感じるなら、正しく腹筋に効いている証拠です。
- 逆に腰や肩に負担がかかる場合は、腹圧を適切に使えていないため、まずは基本から丁寧に行うことが大切です。
- ストレッチポールなどの道具を使えば、姿勢の維持がしやすくなります。
実践のすすめ
動画では「実践編」も別に用意されており、説明を省略したメニューに沿って週2〜3回の継続が推奨されています。腹圧を意識することを習慣化し、テニスのスイングや動作に落とし込むことが本質的な目的です。