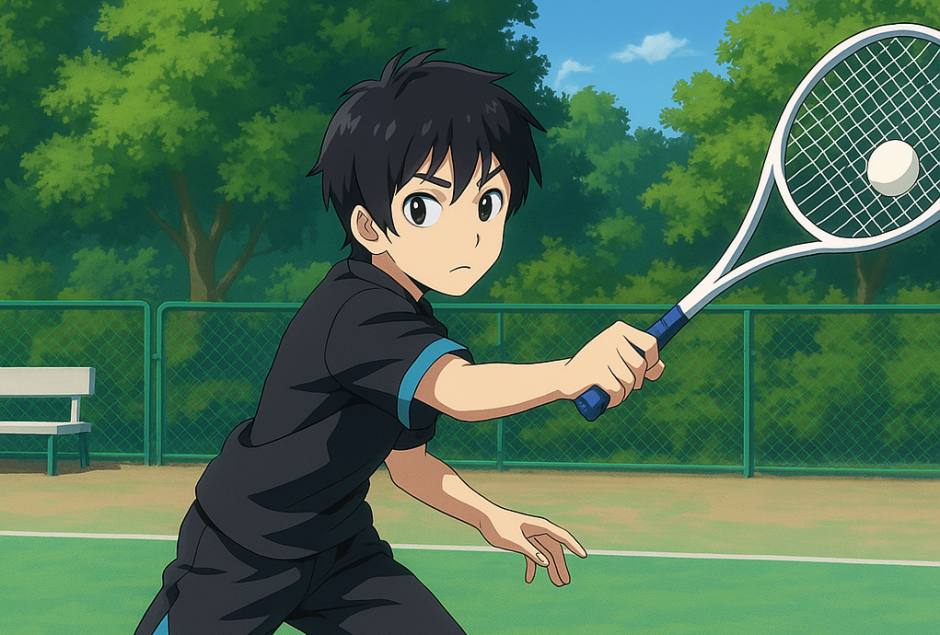ソフトテニス ダブル前衛の戦略 おすすめ5選です。ソフトテニスではダブル前衛・ダブルフォワードと呼びますが、硬式テニスでは並行陣と呼んでいます。硬式テニスのエッセンスも参考にして、ソフトテニスを上達していきましょう。
【ソフトテニス】ダブル前衛のポジションについて
基本的なポジショニングの考え方
試合中のプレーに取り組む前に、まずポジショニングの基本を押さえることが重要です。ボールのバウンドや打球の方向を予測し、効率的な位置取りを行うことが求められます。
クローズに構える重要性
多くの場合、打球に対応するにはクローズドスタンス(体を少し閉じた姿勢)で構えるのが効果的です。特に外側から内側に入ってくるボールに対応する際には、この構えが有効です。
ミドルサーブ後の対応
味方がミドルサーブを打った場合、基本的には相手の正面に立ってボールに備えると良いです。このポジションから、ほとんどのボールに1歩または2歩で対応可能です。
サイドに入った場合のポジション取り
サイドにボールが入ったときは、一度ストレート側に立ってから内側への跳ね返りを意識してポジションを修正します。外側に打たれたボールは内側に戻ってくる傾向があるため、それに備えることが大切です。
ランダム対応時の動き
ランダムにボールが飛んでくる場面でも、実はそれほど大きく動かずに対応できます。適切なポジションをとっていれば、1歩から2歩の移動で十分に対応可能です。
打球のアウト・インの判断
後衛のプレーにおいて、アウトかインかの判断はボールの高さや相手のフォームを見て瞬時に行います。常に相手の打点や軌道を観察することで、的確なポジション修正が可能です。
全体を通じた意識の持ち方
どの角度から打たれても、「ボールがどこを通過するか」を意識することで、自分がどこに立つべきかが自然と見えてきます。先読みではなく、通過点を意識した立ち位置の取り方が重要です。
このような意識とポジショニングを日頃から意識することで、より効率的にボールへ対応できるようになります。練習時から取り入れてみてください。
【ソフトテニス】ダブル前衛が上手い選手の共通点!戦い方・ポジションよりも大切な3つの能力
ダブルフォワードに必要なフットワークとは
本講座では、ダブルフォワードで前衛に詰める際のフットワークについて解説しています。特に上級者が実践している動きに着目し、足運びや姿勢の作り方を詳しく説明しています。
上手な選手に共通する3つのポイント
- サイドステップが速い
- 前に詰めるスピードが早い
- バランスの取れた体勢で打てる
これらの能力は、守備範囲の広さや対応力の高さにつながります。
サイドステップのコツ
足の向きはガニ股にせず、やや内股気味に保つことでスムーズな横移動が可能になります。股関節とお尻の筋肉を使って動くことが、素早いフットワークの鍵です。
前方への動きと姿勢の重要性
オープンスタンスではなく、しっかりと前方に向けた体勢で動くことで、戻り動作もスムーズになります。お尻を支点にした姿勢作りが重要で、膝だけに頼ると姿勢が崩れがちです。
安定した構えと反応力の強化
ボールを打ちながら前に出る際には、倒れ込みすぎないよう注意が必要です。重心を前に保ちながらも、腰をしっかり支えることで反応力が高まり、予期せぬボールにも対応できます。
困った時の姿勢作りとトレーニング法
反応が求められる場面では、姿勢を低く保ち、体幹で支える動きが効果的です。YouTubeなどで紹介されているトレーニングも参考にしつつ、実戦に活かせる技術を磨きましょう。
まとめ:強いダブルフォワードの条件
強いダブルフォワードには、次の要素が必須です。
- サイドステップの速さ
- 前への詰めの速さ
- 安定した姿勢での対応力
これらを習得することで、前衛としての対応力が格段に向上します。
前衛の決定力爆上げ!ダブルフォワード強化のためのハーフボレー&ハイボレー【ソフトテニス】
全日本社会人大会に向けた取り組み
選手が全日本社会人大会に向けてダブルフォワードに挑戦中であり、特にネット前でのローボレーやハーフボレーの技術強化を目指しています。攻撃力を高めるには、この中間ポジションでの安定したプレーが不可欠です。
ローボレーの基本とコツ
ローボレーではラケットを上から下に回すようにして重みを使うことが重要です。手で無理に操作せず、ラケットの面を正しい方向に向けて「運ぶ」ような感覚で打つと安定します。打点は少し前で取り、左手を活用してラケットの面をコントロールすることがポイントです。
流し方向へのローボレーの工夫
流し方向へのローボレーは、逆クロスから来るボールに対して少し後ろで打点をとり、面の角度で方向をつけます。詰まらず、打ちたい方向にラケット面を向けることが成功の鍵です。
ハイボレーの感覚「掴んで飛ばす」
ハイボレーでは「叩く」よりも「掴んで飛ばす」感覚が大切です。この感覚を掴むとインパクトの音が変わり、威力と安定感が増します。正面を向かず、体を横に向けて構えることでタイミングも取りやすくなります。
バックハイボレーの苦手克服
バックハイボレーは多くの選手が苦手としやすいショットです。熟も以前は威力を出せなかったが、「面を残して飛ばす」感覚を掴むことで安定したショットが打てるようになりました。体の向きと面の角度が成功のカギです。
ダブルフォワードとしての成長
ダブルフォワードでは相手の多様な配球に対応する必要があり、ローボレーとハイボレーの精度が問われます。練習を通じて掴んだ感覚を元に、安定性と攻撃力を両立させたプレーを目指しています。
【ダブルス】並行陣のやり方❗️ 〜誰にも言えないけど並行陣ってやり方が逆に結構、微妙に分からない件〜【ジュエ インドア テニス】
平行陣を取るメリットとは?
平行陣を取ることで、相手に対してプレッシャーを与えると同時に時間を奪うことが可能になります。これはダブルスにおいて非常に有効な戦術です。
平行陣を取る具体的な方法
- サービスダッシュ:サーブと同時に前に出る戦術。トスはやや前に上げ、コースを狙ってサーブを打ちます。
- リターンダッシュ:セカンドサーブを狙ってリターンしながら前進する戦術。ライジングやスライスでの対応も有効です。
- ラリー中のチャンスを活用:相手を動かしたタイミング(角度をつけたショットや深いボール、ストレートロブ、ネットプレーなど)で前に出て、時間を奪います。
平行陣を取る目的を明確にする
ただ前に出るのではなく、「プレッシャーをかけたいのか」「時間を奪いたいのか」を意識することで、平行陣の取り方が効果的になります。
後衛のポジションの取り方
後衛は味方前衛と相手ペア2人、合計3人を視野に入れられる位置に立ちましょう。これにより、ペアの動きが見えやすくなり、センターのボールにも対応しやすくなります。基本はサービスライン付近、動きに自信があれば1歩前でもOKです。
前衛のポジションの注意点
前衛はボレーとストロークのテンポに対応できるように、サービスラインから2歩ほど前が理想の位置です。ただし、ストレートロブへのカバーが難しいペアでは、サービスライン上に立つのが安全です。2人並んでプレイする形も選択肢です。
状況に応じたポジションの変化
チャンスボレーやポーチを狙うときは、積極的に前に詰める必要があります。光栄の位置取りが変わると、全衛のポジションも調整が必要になるため、お互いの連携が重要です。
平行陣への挑戦を後押し
タイブレーク形式の練習を通して、実戦での平行陣の活用を学びました。苦手意識がある方も、平行陣を積極的に取り入れて、ダブルス力を高めていきましょう。
【ダブルスはこれで制す!】平行陣3ポイントレッスン!【テニス】
ダブルスにおける平行陣の3つのポイント
今回はダブルスの「平行陣」における基本的な立ち位置・動き・配球のポイントについて、3つの観点から解説されています。
ポイント1:後衛の立ち位置と体の向き
- 後衛はセンター寄りに立つのが基本
外側をカバーしすぎず、あえてクロス側を少し空けて「打たせる」ことでミスを誘う戦術です。 - 体の向きはクロス方向を意識
正面ではなく斜めを向くことで、クロス方向のボールに素早く反応できるようになります。
ポイント2:前衛のポジショニングと動き
- 前衛はセンターラインとシングルスラインの中間に立つ
詰めすぎず、ロブ対策をしながらプレッシャーをかけることが大切です。 - 相手の体勢が崩れたら前に出る
最初からネットに張り付きすぎず、相手の動きに応じて前に出る判断が重要です。 - 動きの自信がない場合はポジションを少し下げる
無理に詰めすぎず、ロブにも対応できるように立ち位置を調整します。
ポイント3:効果的な配球の狙いどころ
- 狙うのは「センター」や相手のバック側の中央
コートの外側を狙うと返球されやすいため、中央に配球して角度をつけにくくします。 - ストレートボレーやドロップボレーで揺さぶる
相手の位置やショットに応じて、攻撃的にボールを運ぶ工夫も必要です。 - 外側を狙いすぎないこと
外を狙うと相手に読まれやすくなり、逆にピンチになるケースが増えるため注意が必要です。
練習のポイント
- 真ん中を狙ったボレーボレーのラリー練習が有効です。
- ポジションや配球の選択を試合形式で確認することが、実践力アップにつながります。